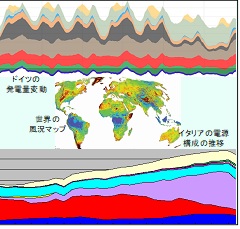
eBook 無料ダウンロード
| データをもとに考える 日本の電源構成の再構築 |
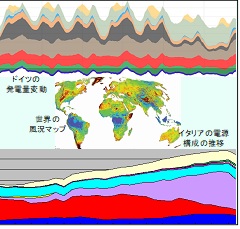
| 本レポートは、福島第一原発の事故の後、見直しが必要になっている電源構成、2015年末のCOP21で表明することが必要な温室効果ガス削減目標、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直しなどを考えるためのデータを紹介しています。
2015年1月 執筆 田中雄三 |
注) PDFですから、どのような表示倍率でご覧になっても
構いませんが、本レポートはA5版として計画したものです。
電源構成の再構築-全体ダウンロード![]() ( 約5 MB)
( 約5 MB)
| 目 次
1.1 脱原発を決めた国の電源構成 1.2 発電電力量が多い国 1.3 各国の電源構成 1.4 世界全体の電源構成 1.5 各電源の発電量上位20ヵ国 1.6 電源の多様化 1.7 各国の電気料金 2. 石炭火力は最大の電力源 3. 原発が果たした役割と今後 4.1 風力と太陽光の発電コスト 4.2 なぜEUは再生可能エネルギーに熱心か 4.3 世界の風力発電の概況 4.4 主要国の風況マップ 4.5 EUの風力資源 4.6 日本の風力資源 4.7 洋上風力の発電コスト 4.8 本項のまとめ 5.1 ドイツの太陽光発電の設備価格 5.2 なぜドイツの太陽光発電は安いのか 5.3 日本と世界の太陽光発電の設備価格 5.4 日本と世界の太陽電池モジュール価格 5.5 太陽光発電の買取価格の決定 5.6 ドイツの太陽光発電買取制度の経緯 5.8 ドイツの太陽光発電の事例から学ぶこと 5.10 日本の太陽光発電の大きな認定量の影響 5.11 太陽光発電の導入想定量と認定量の乖離 6.1 天然ガス利用の現状 6.2 天然ガスの輸入 6.3 原発をガス火力に転換すると 6.4 天然ガスの漏洩による温暖化 7. 中国のCO2排出量はどこまで増加するか 7.2 統計データに対する疑念 7.3 エネルギー指標の推移から考える 7.5 中国CO2排出量の将来予測 7.6 公的機関による中国CO2排出量の予測 7.7 中国のCO2排出量の削減目標 8.1 京都議定書 8.2 GHGの削減量 8.3 森林等吸収分と京都メカニズムクレジット 8.5 2020年代の温室効果ガス削減目標 9. 附属書Ⅰ国とEUの温室効果ガス排出量 9.2 附属書Ⅰ国などのGHG排出量 9.3 GHG排出量の俯瞰的データ 10.1 ドイツの長期エネルギー戦略 10.2 その後の関連法と原発 10.3 長期エネルギー・シナリオ 10.4 主要項目の将来動向 10.5 シナリオ2011Aの主な結果 10.6 再生可能エネルギーによる発電の変動対策 10.7 再生可能エネルギーへの移行の経済影響 10.8 ドイツと日本の違い 10.9 日本独自のシナリオ おわりにデータ出所・参照文献 |
| 本書の概要と掲載図表例 1. 世界各国の電源構成 4. 欧州と日本の風力発電 5. ドイツの事例をもとに考える太陽光発電 6. ガス火力は期待に応えられるか 7. 中国のCO2排出量はどこまで増加するか 8. 日本の温室効果ガス、誰がCO2を増加させたのか 9. 附属書Ⅰ国とEUの温室効果ガス排出量 10. ドイツの再生可能エネルギー拡大の長期シナリオ |
|
2020年以降の温室効果ガス削減目標に関する (筆者のパブリックコメント、2015年6月) 一方、世界の気温上昇を2℃以下に抑える目標や、2050年に先進国全体で温室効果ガス排出量を80%削減するという目標の達成に対し、26%削減では明らかに不充分です。 また、2013年比で26%減は、1990年比では表せば18%減になります。京都議定書の日本の削減目標が90年比6%減でしたから、2030年の目標が90年比18%では、世界5位の温室効果ガス大量排出国、世界3位の経済大国の目標として、諸外国から賛同は得られないでしょう。 ハイブリッド車やLEDの日本での普及は目覚しく、省エネは進展すると思います。また、今度こそ、業務部門や家庭部門のCO2排出削減も期待できるかもしれません。しかし、更に温室効果ガスを削減するには、かなりを再生可能エネルギーの導入拡大に頼らなければならないでしょう。その場合、日本は安価な風力発電の立地が限られているため、発電コストが高い太陽光発電に依存せざるを得ません。 顧みれば、この3年間に実施された再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国の制度として、あまりにもお粗末でした。具体的には、 ①固定価格買取制度は、かなり危うい制度であり、慎重な対応が必要なことは、少し考えれば分かることです。その種の指摘も多数ありました。それにも拘わらず、政治は「制度開始から3 年間は高い電力価格で買取り、発電事業者が充分な投資収益を確保できるようにする」と法律に書き込んでしまいました。 ②太陽光発電の買取価格は、ヒアリング調査をもと決められましたが、発電事業者を代表したいい加減な主張を、ほぼ全面的に受け入れたものとなりました。付け加えれば、買取価格の検討委員会の委員長は、その後、その発電事業者が設立した団体の理事を務めました。 ③太陽電池モジュールは国際的に取引されている商品ですが、買取制度開始時の日本の市場価格は、ドイツなどの諸外国と比べ、極めて高いことが、国際エネルギー機関(IEA)やドイツ太陽光工業協会(BSW)の公表情報で、世の中に知られていました。それにも拘わらず、高い市場価格をそのままに、なんら対策を講じることなしに、高い買取価格が設定されました。 ④高い買取価格を設定すれば、低金利時代にあって安全確実な投資と見做され、太陽光発電のバブルが発生することは、ドイツの事例から想像できたことです。また、その投資収益を負担するのは、主に投資余力が乏しい電気利用者です。財政赤字の政府には都合がよい制度かもしれませんが、電気のような必要不可欠なものに対する国の制度として不適当です。 ⑤太陽光発電バブル発生の危惧が現実になったことは、周知の通りです。再生可能エネルギーを拙速に導入拡大しなければ、必要なかった筈の経済的負担を、電気利用者はこの先20年間に亘り払い続けなければなりません。 再生可能エネルギーを否定する訳ではありません。しかし、どう言い訳をしようと、太陽光発電の発電コストが高い事は明らかです。従って、少ない国民負担で、如何に導入拡大するかが重要になります。 固定価格買取制度を継続するのならば、20年間に亘り初年度価格で買取続ける制度であることを忘れないで下さい。制度開始当初の買取価格が高い段階で、太陽光発電の導入バブルが発生したのでは、電気利用者は堪りません。2030年の削減目標なのですから、拙速に導入拡大を目指すのではなく、先ず、再生可能エネルギーの設備価格低下の対策を講じて下さい。 政治や行政は、過去3年の失敗を反省し、少ない国民負担で温室効果ガスを削減をすることで評価される、ことを自覚して戴きたいと思います。 |